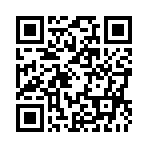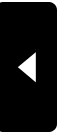2014年09月03日
3000m突破に挑戦 前穂高岳 (重太郎新道コース) (6) 重太郎新道の感想など
さて翌日(8/24)。
目が覚めたのは4時過ぎ。
昨日は7時過ぎには寝ましたので、睡眠時間は充分です。
カーテンをめくって外を見ると、テン泊組はテラスで朝食の準備中です。
朝の薄明から日の出にかけての山の雰囲気を味わいたくて、自分もテラスに出てみました。
薄明の上高地。

雲が重く垂れ込めています。
昨日自分が小屋に降りた頃から山には再びガスがかかり始めたのですが、それが継続しているようです。

となると自分が登った時の快晴は7時過ぎから14時過ぎまでの7時間ほどだったことになります。
今年の夏の状況からすれば奇跡のような一瞬に巡り会ったと言えるでしょう。
それはさておき、今日の予定ですが、確定しているのはお昼過ぎに上高地を発車する平湯行きのバスに乗ることです。
朝食(5時)を終えて、ゆっくり準備をしても6時。
岳沢小屋から上高地まで約2時間。
上高地をぶらつくにしてもかなり時間が余りそうです。
折角だからもう少し山に滞在する時間を長くしたいなと思い、小屋の西側の天狗沢沿いにあるというお花畑を散策することにしました。
お花畑と言ってもルンルン気分で散歩できるような所ではありません。
既にお見せした写真ですが、

バリエーション以外では北アルプス最難関と言われる奥穂~西穂ルート中で唯一のエスケープルート(中央のくびれた個所=天狗のコル)から降る天狗沢ルート、お花畑はこの天狗沢ルート沿いにあります。
「山と高原地図」には「ガレ場の登り、一般向でない」と記載されています。
しかし、小屋にあった説明書きには「やや荒れているが第4お花畑までは危険な個所はない」とのことなので、行ってみることにしました。
小屋の西側に案内表示があります。

こんな感じのガレ沢を登って行きます。
浮石多数あり。

お花畑はガレ沢と別なガレ沢との間にあります。

時期的に花の盛りは過ぎていると思いますが、まだまだ楽しむことができました。
花の写真は日を改めて紹介したいと思います。
天狗沢とコブ沢を隔てる尾根。

ガスがかかって不気味なイメージ。
天狗沢の雪渓。

到達最高地点。

GPSの読みで標高2500mです。
ここに達した時にガスが濃くなって、天気もかなり怪しくなってきたので引き返すことにしました。
何しろ登って行った先には北アルプス最難関とされる困難な岩場が待ち受けていますので、二進も三進も行かなくなって救助要請なんてことにならない様、身の程をわきまえることが肝要です。
少し降った所で、ややガスが切れて天狗岩(天狗の頭)が見えました。

晴れていればもうちょっと迫力のある景色を見ることが出来たと思うので残念。
(昨日あれだけの快晴に恵まれたので、これ以上望むのは無理ってものかも)
半分くらい降った所で、ポツポツきていた雨が急にザッと降ってきました。
あわててレインスーツを着用しましたが、足元の岩は完全に濡れてしまって滑ること。
例のお兄ちゃん、大丈夫かなと頭をよぎります。
小屋に帰り着いた時には9時になってました。
あとは比較的安全な道を上高地に降るだけです。
6:30 岳沢小屋(標高2170m)
7:47 到達最高地点(標高2500m)
9:00 岳沢小屋
という感じで、重太郎新道(+天狗沢ルートの途中)を踏破した感想です。
・重太郎新道に限って言えば、技術的には3点支持をしっかり守れれば問題ありません。
冷や汗を流しながら切り抜けるような個所は1つもありません。
ですが、浮石はあちこちに存在します。また、うっかりすると滑落という個所も満載です。
したがって、できることなら3点支持で登下降できるような岩場で練習しておけばより安心です。
・とはいうものの、決して油断してはいけません。
この夏山シーズン、重太郎新道近辺では遭難が多発しています。
岳沢パノラマ付近でも2件、吊尾根では死亡事故2件を含む3件の事故が発生していますので、充分な注意が必要です。
・重太郎新道で重要なポイントは技術より体力(脚力)でしょうね。
それでも普段からしっかりと山を歩かれている方なら問題はないレベルだと思います。
・装備としてはできればヘルメットを準備しましょう。今回は自分も装着したのですが、見た感じでは装着率は30%くらいな感じです。もうちょっと装着率が上がるべきだと思います。
(追記)
今日、昔の「山と渓谷」を読み返していたら2012年2月号に重太郎新道を下山中に起きた滑落事故の検証記事がありました。
場所はカモシカの立場より少し上の梯子の辺りです。
遭難者は40代の男性、ベテラン。
アルプスをずっと縦走してきて、上高地に降るために重太郎新道を降りていたとのこと。
それまでに岩が濡れた状態の大キレットを無事通過してきたのですが、最後の最後にそれほど難しくない場所で事故が起きてしまいました。
やはり油断は禁物ということを改めて思いました。
目が覚めたのは4時過ぎ。
昨日は7時過ぎには寝ましたので、睡眠時間は充分です。
カーテンをめくって外を見ると、テン泊組はテラスで朝食の準備中です。
朝の薄明から日の出にかけての山の雰囲気を味わいたくて、自分もテラスに出てみました。
薄明の上高地。
雲が重く垂れ込めています。
昨日自分が小屋に降りた頃から山には再びガスがかかり始めたのですが、それが継続しているようです。
となると自分が登った時の快晴は7時過ぎから14時過ぎまでの7時間ほどだったことになります。
今年の夏の状況からすれば奇跡のような一瞬に巡り会ったと言えるでしょう。
それはさておき、今日の予定ですが、確定しているのはお昼過ぎに上高地を発車する平湯行きのバスに乗ることです。
朝食(5時)を終えて、ゆっくり準備をしても6時。
岳沢小屋から上高地まで約2時間。
上高地をぶらつくにしてもかなり時間が余りそうです。
折角だからもう少し山に滞在する時間を長くしたいなと思い、小屋の西側の天狗沢沿いにあるというお花畑を散策することにしました。
お花畑と言ってもルンルン気分で散歩できるような所ではありません。
既にお見せした写真ですが、
バリエーション以外では北アルプス最難関と言われる奥穂~西穂ルート中で唯一のエスケープルート(中央のくびれた個所=天狗のコル)から降る天狗沢ルート、お花畑はこの天狗沢ルート沿いにあります。
「山と高原地図」には「ガレ場の登り、一般向でない」と記載されています。
しかし、小屋にあった説明書きには「やや荒れているが第4お花畑までは危険な個所はない」とのことなので、行ってみることにしました。
小屋の西側に案内表示があります。
こんな感じのガレ沢を登って行きます。
浮石多数あり。
お花畑はガレ沢と別なガレ沢との間にあります。
時期的に花の盛りは過ぎていると思いますが、まだまだ楽しむことができました。
花の写真は日を改めて紹介したいと思います。
天狗沢とコブ沢を隔てる尾根。
ガスがかかって不気味なイメージ。
天狗沢の雪渓。
到達最高地点。
GPSの読みで標高2500mです。
ここに達した時にガスが濃くなって、天気もかなり怪しくなってきたので引き返すことにしました。
何しろ登って行った先には北アルプス最難関とされる困難な岩場が待ち受けていますので、二進も三進も行かなくなって救助要請なんてことにならない様、身の程をわきまえることが肝要です。
少し降った所で、ややガスが切れて天狗岩(天狗の頭)が見えました。
晴れていればもうちょっと迫力のある景色を見ることが出来たと思うので残念。
(昨日あれだけの快晴に恵まれたので、これ以上望むのは無理ってものかも)
半分くらい降った所で、ポツポツきていた雨が急にザッと降ってきました。
あわててレインスーツを着用しましたが、足元の岩は完全に濡れてしまって滑ること。
例のお兄ちゃん、大丈夫かなと頭をよぎります。
小屋に帰り着いた時には9時になってました。
あとは比較的安全な道を上高地に降るだけです。
6:30 岳沢小屋(標高2170m)
7:47 到達最高地点(標高2500m)
9:00 岳沢小屋
という感じで、重太郎新道(+天狗沢ルートの途中)を踏破した感想です。
・重太郎新道に限って言えば、技術的には3点支持をしっかり守れれば問題ありません。
冷や汗を流しながら切り抜けるような個所は1つもありません。
ですが、浮石はあちこちに存在します。また、うっかりすると滑落という個所も満載です。
したがって、できることなら3点支持で登下降できるような岩場で練習しておけばより安心です。
・とはいうものの、決して油断してはいけません。
この夏山シーズン、重太郎新道近辺では遭難が多発しています。
岳沢パノラマ付近でも2件、吊尾根では死亡事故2件を含む3件の事故が発生していますので、充分な注意が必要です。
・重太郎新道で重要なポイントは技術より体力(脚力)でしょうね。
それでも普段からしっかりと山を歩かれている方なら問題はないレベルだと思います。
・装備としてはできればヘルメットを準備しましょう。今回は自分も装着したのですが、見た感じでは装着率は30%くらいな感じです。もうちょっと装着率が上がるべきだと思います。
(追記)
今日、昔の「山と渓谷」を読み返していたら2012年2月号に重太郎新道を下山中に起きた滑落事故の検証記事がありました。
場所はカモシカの立場より少し上の梯子の辺りです。
遭難者は40代の男性、ベテラン。
アルプスをずっと縦走してきて、上高地に降るために重太郎新道を降りていたとのこと。
それまでに岩が濡れた状態の大キレットを無事通過してきたのですが、最後の最後にそれほど難しくない場所で事故が起きてしまいました。
やはり油断は禁物ということを改めて思いました。
Posted by あいあん at 23:07│Comments(0)
│山登り